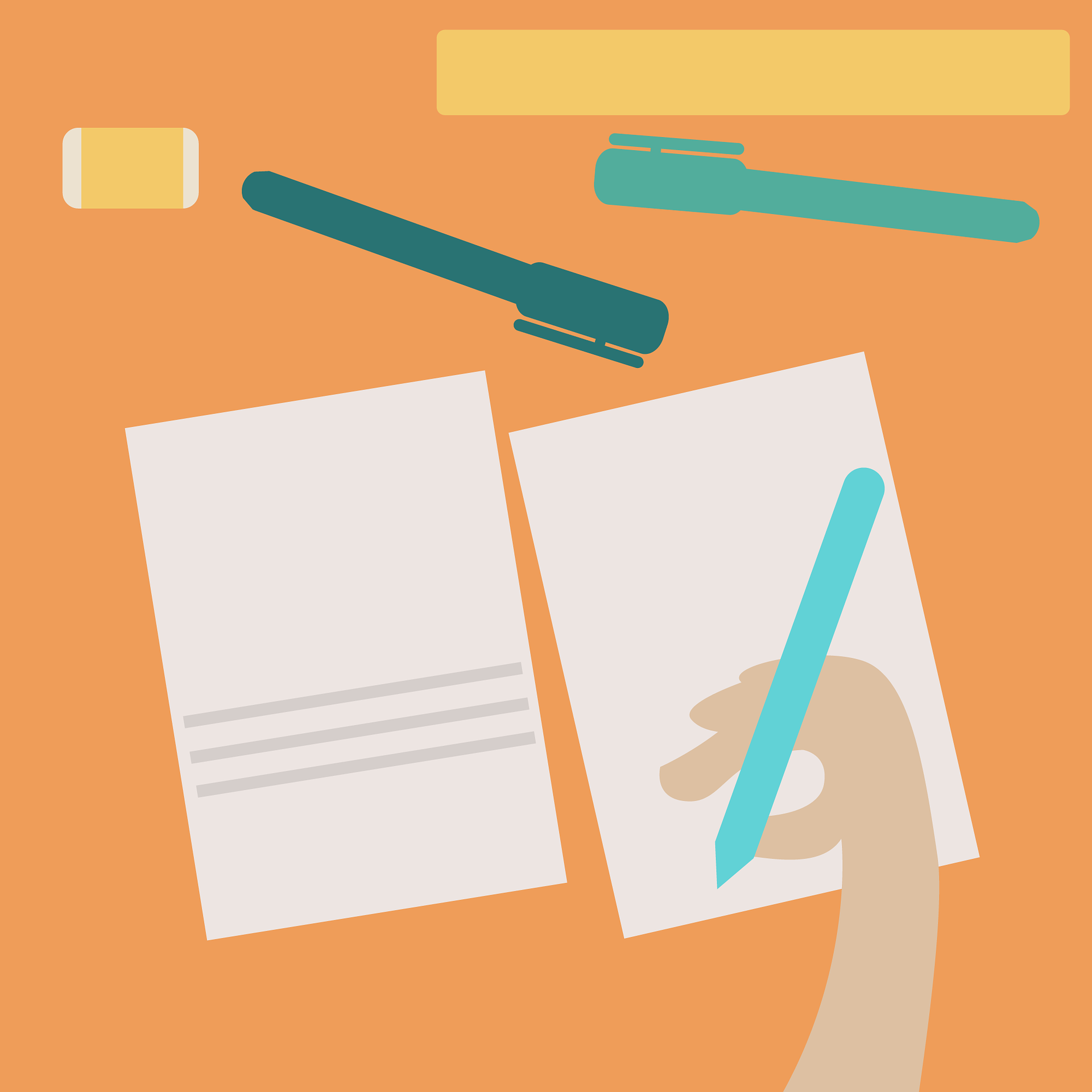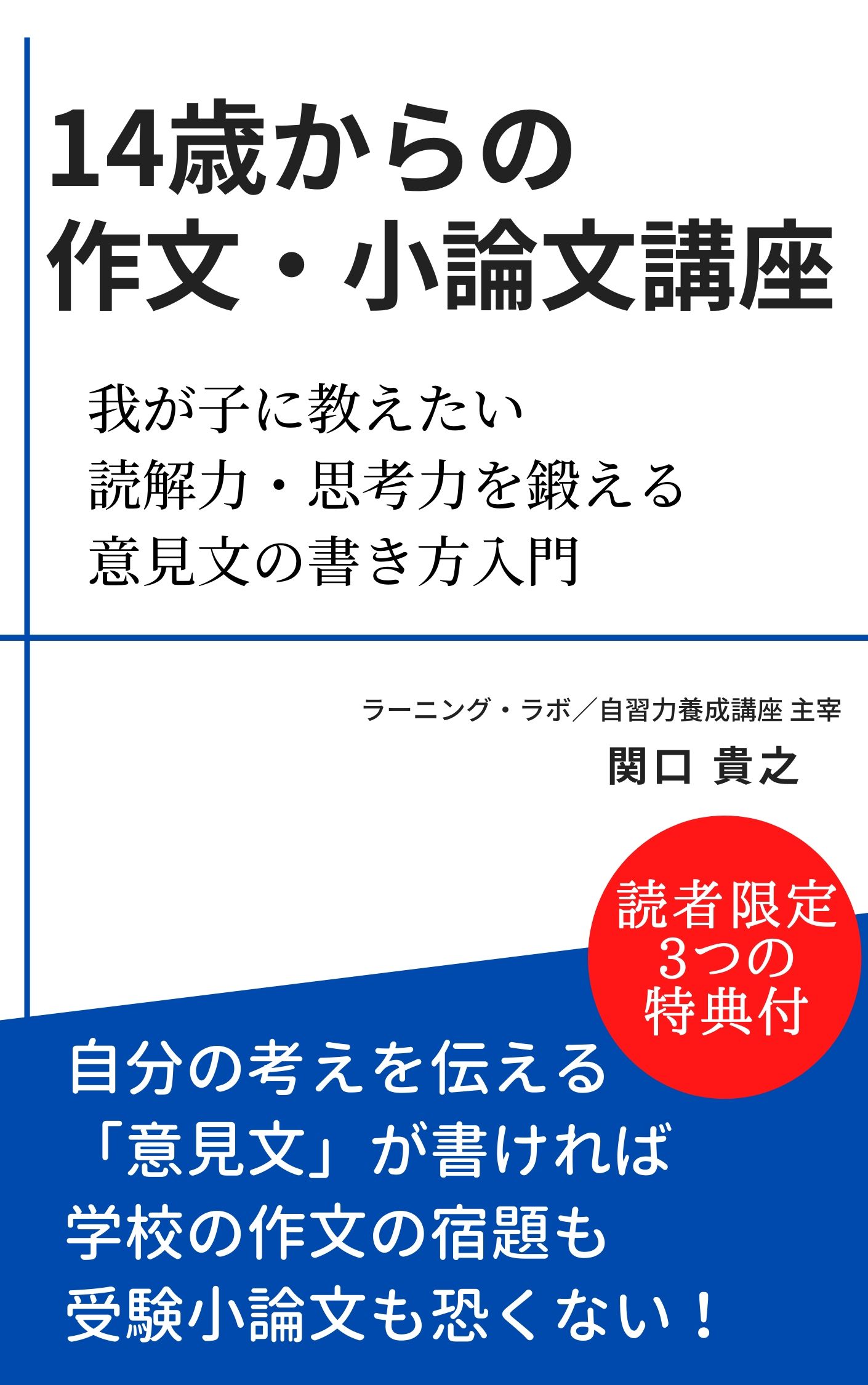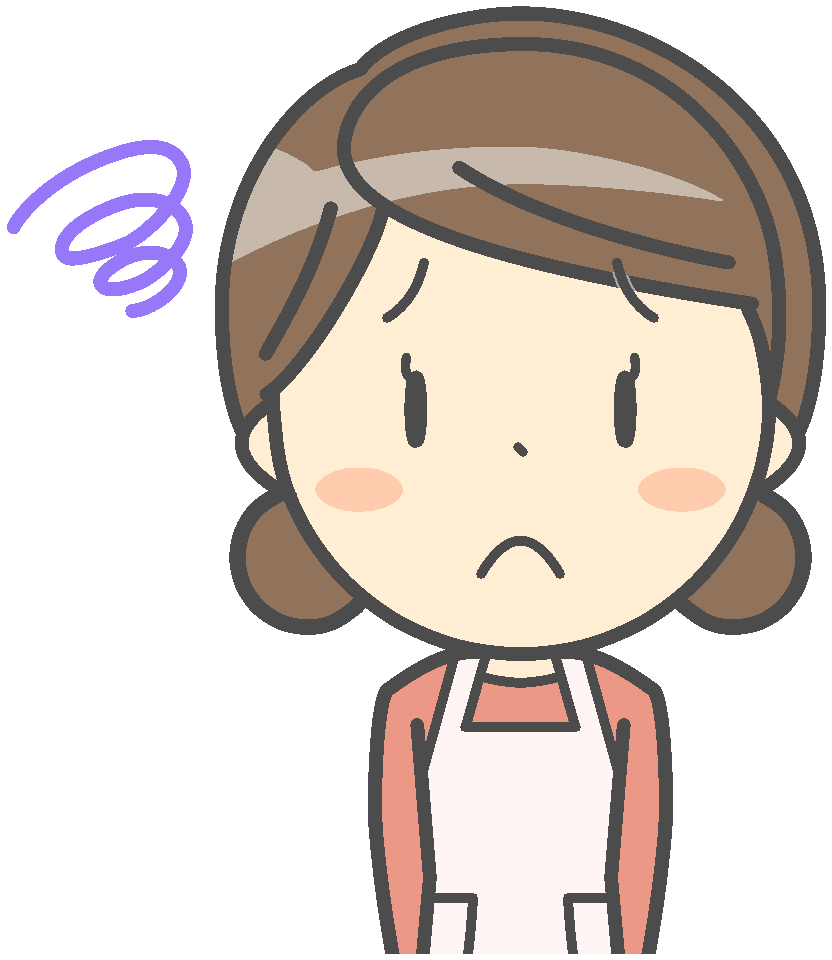
最近は学校でも作文など文章を書く作業が増えている気がする。

でも、学校で「作文の書き方」って実は習っていない・・・
入試でも作文・小論文はもちろん、記述問題など「書く」問題があります。
仕事や日常生活など学校以外の場面でも自分の意見を書く場面はたくさんあります。
入試の面接や就職の面接、仕事のプレゼンなど「話す」場面でも原稿を書く作業があります。
学校でも習っていないのに、いったいどうやって作文を書けばいいのか、小論文なんて難しそうで何から手を付ければいいかわからない・・・
そんな作文の書き方に関するお悩みに答えるため、この記事では、作文の書き方、特に、小論文などに代表されるような自分の意見を書く文章(意見文)の書き方を解説したいと思います。
この記事でわかること…
これから作文の書き方についてお話しするのですが、そんな僕も実は学生時代、作文は苦手でした。
というより、学校では作文の書き方なんて教えてもらった記憶がありません。
それなのに、夏休みには読書感想文、行事のあとには感想文が定番で、当時は、わけも分からず、とりあえず原稿用紙を字で埋めていましたね。
近頃は、中学生では「人権作文」や「税の作文」を書くのが定番化しているようです。
僕が中学生の頃にはなかったと思いますが、あの頃いきなり人権作文を書けと言われたら、相当苦しんでいたはずです。
ちなみに、僕は、神奈川県内で20年以上塾講師として、小学生、中学生、高校生の学習指導をしてきました。また、大人になってから教育をちゃんと学び直そうと思い、大学院に入学して教育について研究もしています。その時専攻していたのが国語教育ということもあり、読解・作文指導は他の教科よりも力を入れている分野です。
高校・大学入試の作文や小論文はもちろん、大学生や社会人の方の文章作成の指導も行っています。最近では、大人の方が、文章がうまく書けずに困っているという場合も少なくない印象です。
ですので、読解・作文に関して何かお悩みや相談したいこと、こんな話が聞きたいというリクエストがあれば、ぜひ遠慮せずにお問合せフォームからメッセージをください。
なお、作文の書き方については、動画も公開しています。

2021年4月28日現在、約15万回再生されています。
この記事の最後に、動画閲覧ページのリンクを貼り付けておきますので、記事の内容と合わせてご覧頂ければうれしいです。この動画講座は3部作となっていて、書き方のレクチャーから、実際に作文を作成する過程を実況中継的に紹介するものもあります。ぜひ合わせてご覧ください。
なお、Googleで「作文の書き方」と検索し、「動画」をクリックしてもらっても出てきます。
ぜひ検索してみてください。

■作文・小論文の中上級者、大学入試受験生の方は、ぜひこちらの記事を合わせてご覧ください。
作文・小論文(意見文)を書くための3つのポイント
作文の書き方といっても、この記事では、小論文や意見文などの実用的な文章である文章を書く方法についてお話ししていきます。
作文が苦手な初級者の方が「自分の考え・意見を伝える文章」を作成するための方法が中心のテーマです。
自分の考え・意見を伝える文章ということは、当然、伝える相手がいます。
文章なので、読者と言っても良いですね。
ですから、相手・読者にあなたの考え・意見が「ちゃんと」伝わる文章を書く必要があります。
せっかく書いた文章が誤解されては意味がありませんからね。
ということは、作文を書く時にまず意識しなければいけないこと、それは「わかりやすい文章を書くこと」といえます。
では、「わかりやすい文章」、つまり、あなたの考え・意見を相手に誤解されない文章を書くために必要なことは何でしょうか?
まずは次の3点に注目しましょう!
以下、それぞれかんたんにポイントをまとめておきます。
作文の書き方【初級編】① 一文(主語-述語)
文章を書くときに、まず意識しなければならないのは「文」です。
自分が何か伝えたいことがある場合、単語だけでは表現できません。
例えば、
「先生、トイレ」
などのフレーズは教室でよく聞くセリフです。
おそらく「先生、トイレ(に行きたいので行っても良いですか?)」という意味で使っているのでしょう。
もちろん、教室で、先生と生徒の関係という状況があれば、「先生、トイレ」とだけ言っても伝わるかもしれません。
しかし、これが別の場所や、別の関係性の人との間での会話であれば、相手が「この人何言ってるの?」となっても不思議ではありません。
特に、作文は「書き言葉」ですから、書かれた言葉のみで相手にメッセージを届けなければいけません。しかも、誤解されないように。
ですから、「誰が」「何を」「どうするのか」といった、基本的な「文の成分」をしっかりと意識して書く必要があります。
特に、「文」の中心は「主語」と「述語」なので、「主語」と「述語」の対応が適切なのかは十分注意する必要があります。
例えば、次のような文はよくある「主語」と「述語」の対応がおかしい文です。
【例文】私の夢は将来医者になりたいです。
この文では、主語が「(私の)夢」なので、述語は「なることです」などにしなければいけません。逆に、述語をこのまま「なりたいです」にするなら、主語と「私は」にしなければいけません。
このように「主語」と「述語」の対応関係が正しくないと、意味がよくわからない文となってしまいます。
ここまでの文はさすがに書いていないという自信のある方も、意外に主語-述語が対応していない文を書いていることがあります。特に、メールの文などではよく見かけます。
ぜひ今一度、自分の作文の「主語」「述語」に注目しましょう。
作文の書き方【初級編】② 接続語
さて、「主語」と「述語」を意識して「文」が正確に書けるようになったら、次は、「接続語」に注目します。
文章は、ひとつの文だけではなく、たくさんの文で出来上がっています。ですから、文と文をつないでいく必要があります。
その「文と文」をつなぐ働きの言葉が「接続語」です。
特に、自分の考え・意見を伝えるための「意見文」「小論文」では、重視すると良い接続語があります。
特に重要な接続詞
なぜ、この3つの接続詞が大事なのか、わかりますか?
自分の考え・意見を伝えるためには、「自分が言いたいこと(=主張)」をはっきりと言う必要があります。
ですが、それだけでなく、「なぜそう考えるのか(=理由)」「なぜ自分の考えが正しいと言えるか(=根拠・証拠)」が必要です。
さらに、「自分の言いたいこと」を伝えるためには、「逆の立場やちょっとちがう立場の意見(=反論)」にもふれておくとより良い文章になります。
例えば、何人かの人と一緒にランチに行くとして、中華に行きたい人と日本蕎麦を食べたい人がいたとします。
日本蕎麦を食べたい人の言いたいこと(=主張)は、「私はそばを食べたい」ということです。
みんなをそば屋さんに連れていきたいので、そばの魅力を語ります。それらが主張の理由や根拠となるものです。
同じように、中華に行きたい人は中華の魅力を語るはずです。
それだけだと、どちらも良いものに見えてきて、話がまとまりません。
そこで、そばを食べたい人が、中華の魅力に触れながら、中華よりもそばの良い点を語ってみたとします。
例えば、こんな感じです。
こう言えば、単に「そばが良い」とだけ言うよりも、そばを食べに行く確率が増えるかもしれませんね。
この例文で示したように、逆の立場や自分とはちょっと違う立場にもふれながら、「でも」という逆接の接続詞を使って、自分の言いたいこと(=主張)、理由や根拠を述べるという形がよく使われます。
もちろん、他にも接続語はたくさんありますが、まずはこの3つの働きをする接続語は、作文(意見文・小論文など)には欠かせないものです。
ぜひ、この3つの接続語から使いこなせるようにしていきましょう。
作文の書き方【初級編】③ 文章の「型」
作文を書く時に、「原稿用紙何枚も書けない」とか「何を書けば良いかわからない」と思ったことはありませんか?
そうした悩みを持ったことがある方は、文章には「型」があるということを知らない場合が多いようです。
作文と聞くと、何もないところから、自分で何かを生み出し、空白の原稿用紙をたくさんの文字で埋めていかなければいけない・・・
そんなこと自分にできない・・・
などと思ってしまっている気がします。
でも、文章には「何を書くべき」で、「どのように書くべき」かという決まった形=「型」があります。
代表的な「型」は、物語文などの「起承転結」というやつです。
ただ、この記事でお話ししている「意見文」では、「起承転結」は少し使いづらい「型」です。
では、意見文で使いやすい「型」ってどんなものがあるのかと言えば、国語の授業で聞いたことがあると思いますが、「はじめ・なか・おわり」=「序論・本論・結論」というやつです。
作文を書き始めたけど、
「途中で止まってしまった」
「原稿用紙4枚も5枚も書けない」
「話があっちに行ったり・こっちに行ったりで何を言いたいのかよく分からなくなってしまった」
などという場合は、この「型」に合わせて作文する練習をくり返すことで改善するはずです。
とはいえ、「はじ・なか・おわり」と言われても、具体的に何を書いていけば良いのかよく分からないという方もいると思います。
「型」というのは、とても大事なものなので、もう少し具体的にお話ししていきます。
文章の「型」に合わせて作文を書こう!
意見文でよく使われる「型」が「はじめ・なか・おわり」=「序論・本論・結論」だとお話ししましたが、より具体的にどんなことを書いていくのかをお話しします。
自分の考え・意見を伝えるためには、大きく3つのことを書く必要があります。
です。
これらを「型」に当てはめてみるとこんな感じになります。
「はじめ」
↓
「なか」
↓
「おわり」
こんな感じです。
さらに、わかりやすいように、先ほどお話しした「そば屋」の例を当てはめてみましょう。
「はじめ」
↓
「なか」
↓
「おわり」
こんな感じになります。
作文を書くとなった時に、原稿用紙を前に1行目の1マス目からフリーズしてしまう人は、特に、文章は「どんな要素」が「どんな順番」で書かれているのかをまず知りましょう。
そして、それぞれの要素ごとに、どんな内容を書くのかを決めていけば、しっかりと筋の通った「わかりやすい文章」が書けるようになります。
とはいえ、この文章の「型」を知ったとしても、すぐには書き始められない人が多いと思います。
また、「えいッ!」と勢いで書き始めても、途中で文が続かなかったり、予想以上に短くなってしまったり、という問題も起こってしまうはずです。
そこで、大事なのが、書く前の「準備」です。
では、どんな「準備」をすれば良いのか、まとめておきます。
作文は書く前の準備で80%が決まる!
作文を書く前に必要な「準備」とは、ズバリ「メモ」です。
書くべき内容は先ほどお話ししたように、ある程度決まっています。
また、それぞれの内容をどの順番で書いていくかも、ある程度決まっています。
ですから、作文を書く前に、まずは、それぞれどんなことを、どのくらい(何文字くらい)書くのかを決めておく作業をします。
書く前に文章全体を見渡して、どんなことを、どの程度書くのかが分かる「メモ」を用意しておけば、途中で迷ったり、字数が足りなくなったり、などということはなくなります。
「メモ」をしっかりと作成し、「あとは書くだけ状態」にしてから、原稿用紙に文字を書き始めるのです。
もちろん、数十文字の文であれば、あえて「メモ」をしなくても書けてしまうかもしれません。あるいは、原稿用紙1枚程度なら書けてしまうという人も多いかもしれません。
ただし、原稿用紙が数枚、千文字前後かそれ以上の文章であれば、書く前の「メモ」を作成するようにしましょう。特に、原稿用紙2~3枚の作文の宿題などで、上手くいかなかった経験のある人は、必ず「メモ」を書きましょう。
僕自身も、今では原稿用紙数枚程度なら「メモ」を準備してなくても、ある程度は書けるようになりましたが、それでも文章を書く前には「メモ」を作っています。それこそ論文などの数千文字、数万文字の文章の場合は、「メモ」がなくては書けません。
まずは、文章の「型」+書くべき内容(主張、理由・根拠、反論)に合わせて、それぞれどんな内容を、どのくらいの字数で書くかを決めましょう。
ポイントは、その「メモ」を見ただけでも、だいたいどんなことを言いたいのかが分かるように書くということです。
作文・小論文(意見文)の書き方【初級編】3つのポイント まとめ
さて、この記事では作文の基礎として、まずは大事な3つのポイントをご紹介しました。
さらに、文章を書く前に「メモ」を作成することが大事だとお話ししました。
ここまでで、作文をする上で大事なポイントをおさえ、大まかに全体像がイメージできたら、さっそく文章を書いてみましょう。
まずは文章の「型」に合わせて「メモ」を作成してみてください。
必要な文字数なども決めておきましょう。
「メモ」を見ただけでどんな作文なのかがイメージできるのが理想です。
いざ書き始めて、途中で迷ったときでも、「メモ」を見れば大丈夫という状態になってから、実際の文章を書き始めましょう。
【動画版】作文・小論文(意見文)の書き方
冒頭でご紹介した「作文(意見文)の書き方」の動画の閲覧ページです。
基本的な作文の書き方のイメージが持てたら、すぐに「書く」という実践にうつりましょう。どんなに知識があっても、実際に書いてみないことには始まりません。
行動して、改善して、また行動・・・
どれだけの密度でこれをくり返せるかが上達のカギです。
では、さっそく書きはじめてみましょう!
疑問点等あれば遠慮なくご相談ください。
なお、「作文・小論文の書き方」について、しっかりと学びたい方に向けて、本を書きました。
この記事でふれていない内容も入った「意見文の書き方入門書」です。
読解力や思考力を鍛えながら作文力(文章を書く力)を身につけていくための練習方法などもまとめています。
ぜひ、ご活用ください。
■本に関する詳細は↓こちら↓
「14歳からの作文・小論文講座:我が子に教えたい読解力・思考力を鍛える意見文の書き方入門」
■この記事では主に意見文の書き方についてお話ししましたが、小中学生にとっては「読書感想文の書き方」も課題のひとつになっている場合があると思います。「読書感想文の書き方」については、ぜひ以下の記事をご覧ください。
■効果的・効率的に「成果を出せる」勉強方法について知りたい方は、ぜひこちらの記事も合わせてご覧ください。タイトルに「中学生の勉強法」とありますが、小学生でも高校生でも(場合によっては大人でも)役に立つ内容になっています。
【中学生の勉強法】4ヶ月で全教科90点以上にした学習方法(超基礎編)
作文以外にも「勉強の仕方」や「勉強習慣の身につけ方」などについて知りたい方は、下のバナーをクリックして「自習力養成講座無料メルマガ講座」にご参加ください!